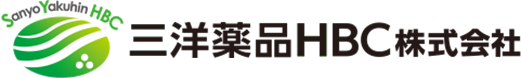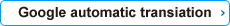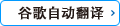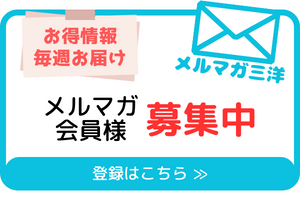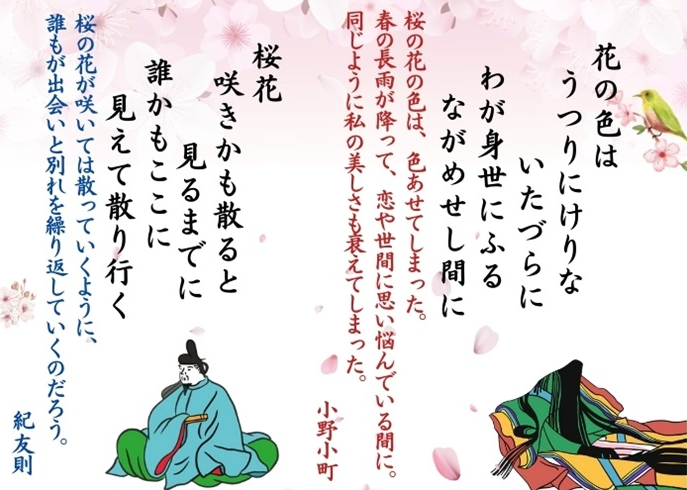
2025/04/11
今や、世界中で愛される桜-桜の魅力を探る、日本の歴史―
🌸桜の歴史🌸
「春を呼ぶ使者」とも呼ばれる桜にはたくさん種類がありますね。
そのうち日本で古くから存在する野生種は、こちらの3種です。
1.ヤマザクラ・・・江戸時代まで花見といえばヤマザクラ。昔和歌で読まれていた桜はヤマザクラを指します。
2.エドヒガン・・・長生きする種であり、特に樹齢が長い立派な樹木は天然記念物に指定されているものもあります。
3.オオシマザクラ・・・伊豆諸島の大島などに自生していた野生種で花弁が白いのが特徴です。
あれ?と思う方・・・
みなさんがニュースとかで良く耳にする桜といえば「ソメイヨシノ」でしょうか。
実は「ソメイヨシノ(染井吉野)」はエドヒガン(江戸彼岸)とオオシマザクラ(大島桜)による種間交雑でできた品種なのです。
名前の由来は、現在の東京都豊島区駒込にあたる当時の染井村からつけられたそう。
染井村には植木職人が多くおり、接ぎ木苗が作られたと推測され、その苗の初期成長が早い上に、大きくて美しい花がつくということがわかり各地に広まっていっただろうと言われています。
🌸桜が親しまれるようになった理由🌸
先月の日記で「桃の節句」についてお話しましたが、「桃の節句」はもともと中国から伝わったもので、春を祝い無病息災を願う厄払いの儀式で「桃」や「梅」を使用していました。
いずれも中国から持ち込まれた植物で日本には自生しない植物だったと言われています。
日本では「桃」や「梅」は、貴族社会で大切にされてきましたが、平安時代に入ると、身近な桜をもっと愛そうということになり、儀式的には意味はないですが、行事に桜が用いられたり、和歌で詠まれたりするようになりました。
春の花の象徴として桜が詠まれるのは平安時代の「古今和歌集」からで、桜を愛でる文化が生まれたのは、この時代からだろうと推測されます。
出典:農林水産省aff(アフ)2023年3月号「日本桜の歴史」より
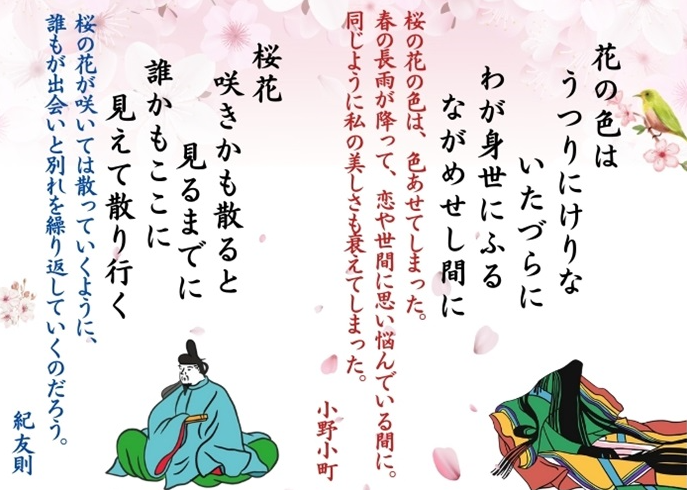
三洋薬品HBCでは、毎週金曜日にテーマを変えてメールマガジンをお届けしております。
メルマガ会員募集中です!登録はこちらから👇